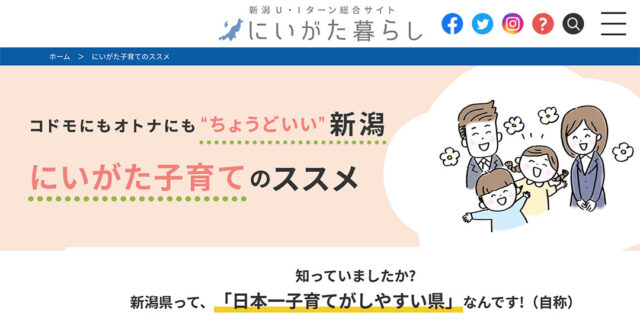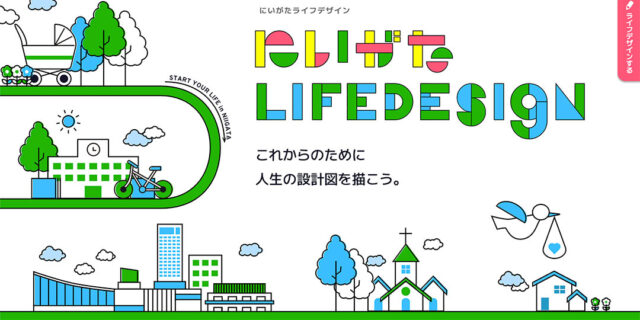新潟県は1歳児を見る保育士の数が倍!?
こどものすこやかな発達のために
県が独自で取り組んでいること | Page 2
目次
なぜ1歳児を国の基準の倍に?
新潟県の保育団体が独自に調査した結果とは

それでは、1歳児の保育を手厚くすることで、どのような効果があるのでしょうか。
このことについては新潟県私立保育園・認定こども園連盟(日本保育協会新潟県支部)が2019年に、関わり・見守りのシミュレーションを行いました。
1歳児クラスの昼食時間中に、テーブルについた3人のこども、6人のこどもの食事をそれぞれひとりの保育者が介助します。時間をずらして行い、こどもの人数は異なりますが、メニューの内容も保育者も同じ。食べ始めから10分間の様子を録画・録音し、保育者がそれぞれのこどもへの声かけの数を数えた結果を比較した、というものです。

その結果、こどもが3人のとき、声かけは平均64回、こどもが6人のときは平均31回となりました。つまり、こどもの数が倍になると、言葉をかけられる数は約半分ほどまで減っていたのです。
さらに、3人のグループでもっとも声かけが少なかった子と多かった子の差は4.6倍(160語対35語)、6人のグループでは最大18.7倍(54語対3語)となりました。これは、6人のグループのときは、3人のグループのときに比べ、「声をかけられる子」と「声をかけられない子」の差が大きかった、ということを示しています。

成長するにつれて月齢による発達の差はなくなっていきますが、特に発達の月齢差や個人差が大きいのが1歳児。こどもの人数が多いと、介助がかなり必要なこどもがいたときに、ほかの子が介助を必要としていても対応できないことがあるのだそう。この調査に参加した保育士からは、「こども6人に対して保育士ひとりの配置では特に手のかかる子への対応が多くなり、ひとりで食事できる子に対しての声かけが少なくなった」という声もあがりました。

保育が手厚い新潟県で
子育てしよう!

安心してこどもを預けられることは、すべての親が望むことですよね。月齢による発達の差が大きい1歳児は、0歳児の子たちよりもできることが増えるものの、まだまだ手がかかります。保育士の配置を倍に増やすことで、保育の質を高め、すこやかに成長できるよう支援している新潟県で子育てしてみませんか?
credit | text:栗本千尋
- 1
- 2