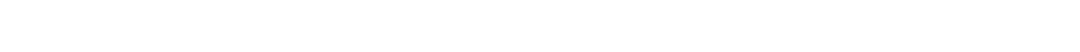“ニットといえば新潟”といわれる時代を目指して

通販会社のバイヤーからのオファーを受け、自然環境に配慮した無染色カシミヤなどを原料とするホールガーメント製品のファクトリーブランド〈LUYUANROSE〉を2011年に立ち上げた佐野さん。この経験により、消費者に届くまでのルートが短ければ、品質の良い製品を手頃な価格で届けられることを佐野さんは実感したそう。
ファクトリーブランドを増やしていく必要を感じ始めていたのと同じ頃、三条市のコンサルティング業務を手がけることになった〈中川政七商店〉の中川政七さんと出会います。

〈丸正ニットファクトリー〉の高い製造技術と、素材への深い知識を土台としたものづくりに興味を持った〈中川政七商店〉。いくつかのやりとりを経て、〈丸正ニットファクトリー〉が“パートナーファクトリー”として素材やデザインの提案と生産を、〈中川政七商店〉がブランディングと販売を手がけるという、OEMでもファクトリーブランドでもない新しいかたちのブランド〈kuru〉が誕生しました。

〈中川政七商店〉とパートナー関係を結び、既存の枠にとらわれないスタイルで立ち上がった〈kuru〉。実際に製品をつくるなかで、新たな発見もあったと佐野さんは言います。
素材へのこだわりとストーリーが生む、新たな“価値”
1716年に奈良で創業し、手績み手織りの麻織物をつくり続けてきた〈中川政七商店〉。年間30万枚を売り上げるという、奈良県産の蚊帳生地を使用した〈花ふきん〉をはじめ、いくつものヒット製品を手がけてきた彼らの、妥協しない素材選びに驚かされたという佐野さん。
「僕だったら商品の価格をおさえるために、素材のクオリティを少し落とすことを選びますが、彼らは正反対。ちょっとしたこだわりを実現するために、より品質も価格も高い素材を選ぶんですね」

またギフト需要の高い〈中川政七商店〉ならではのパッケージの仕方にも、驚きがあったそう。
一般的なお店でニットを買った場合、ラッピングの指定をしない限り、簡単に包装されたものをショッピングバッグに入れられるのが普通です。でも〈kuru〉の場合は、ギフトボックスとしてもひけをとらない専用のボックスに、1着ずつ入れられた状態で手元に届きます。
たとえ中身がわかっていたとしても、ボックスのふたを開ける瞬間は、ついつい気持ちが高まるもの。この製品を選ぶときだけでなく、手にしたときにも付加価値を感じられる工夫について「僕らはニットの素材やデザインの提案はできますが、パッケージや製品の見せ方のアイデアまでは出てこない。こういった部分のセンスの良さは『さすが中川さん!』と思いますね」と佐野さん。

そんなやりとりを通して、あらためて“ブランド“というものについて考えたという佐野さん。「お客さんが製品を見たとき、その背景にある歴史やストーリーに共感し、高い値段でも買いたいと感じてもらえるのがブランド。この付加価値の見せ方は、OEMでは学べなかったことですね。言葉は悪いですけど、やっぱり下請けのようなかたちで製品をつくっていたら、“ブランド”という概念自体をつくり手は持てないなって」
「商社にしてもアパレルメーカーにしても、数量ベースで見たら流通している製品の98%は海外で生産されたもの。そんな状況だからこそ、見附では大量生産をやってはいけない、良いものをしっかりつくればいい……そういうことを〈kuru〉はスタート時から言ってくれているのかもしれないです」

“ニットといえばイタリア”とヨーロッパで言われるように、いつか“ニットといえば新潟”となればいいと話していた佐野さん。「でも、まだ日本の人たちに対しても見附市や新潟のニットの良さをアピールできていないので、まずはそこをちゃんとしないといけませんね」
古い生産体制から脱却し、時代に沿ったスタイルでのものづくりのなかで誕生した〈kuru〉。このブランドによって見附市のニットだけでなく、新潟生まれのニットに新たな“価値”がプラスされる日も、そう遠くないのかもしれません。
Information
credit text:林みき photo:斎藤隆悟