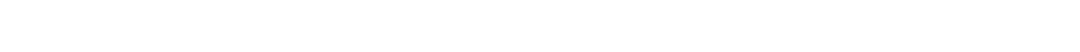江戸時代から続く染物屋〈越後亀紺屋 藤岡染工場〉とは?
新潟駅から車で東に約30分。新潟平野を潤す阿賀野川や、白鳥が飛来する「瓢湖(ひょうこ)」など、水に恵まれた阿賀野市(旧水原町)に、約270年にもわたって染色の技術を継承する〈越後亀紺屋 藤岡染工場〉があります。

寛延元年(1748年)、糸染め屋として創業した藤岡染工場。時代とともに文字や柄を染める印染め屋へと転向し、火消しが羽織る半纏や、祭のハッピ、暖簾などを手がけてきました。
近年、力を入れているのが「手ぬぐい」。新潟を象徴する、さまざまなモチーフが描かれた手ぬぐいは、新潟を訪れたことがある人なら、きっとどこかで目にしたことがあるはず。

これらの手ぬぐいの企画、デザイン、制作を行う染物職人が野﨑あゆみさん。藤岡染工場の次女として生まれ、大学進学にあわせて阿賀野市を離れましたが、大学卒業後は家業に携わるためUターン。
「社長である父が8代目、専務を務める兄が9代目になります。父と兄は営業を担当しているので、私と6人の職人が工場で作業をしています」
ふたりの兄姉がいたこともあり、家業を継ぐことはまったく考えていなかったという野﨑さん。それがなぜ、染物職人に?

染物を生まれて初めて身近に感じた大学時代
もともとデザインに興味があったことから、高校卒業後は長岡造形大学へ。同じ新潟県内でも車で1時間以上かかるため、長岡市に移り住みます。
「視覚デザインを勉強したくて、大学に進学しました。あらゆるデザインの基礎が学べる“産業デザイン学科”を専攻したところ、偶然にも染物の教授に出会ったんです。視覚、工芸、さまざまに学んでいくなかで、紙にプリントされるものより、生地に染めあがる風合いのほうがいいなあと思うようになって。染色の作業もすごく楽しくて、途中で方向性をものづくりに変えてしまいました」
また大学の夏休み中には、手ぬぐい専門店で短期アルバイトを経験。そのとき、いままで気にもしていなかった手ぬぐいの魅力に引き込まれたといいます。
「実家では、昔から半纏や、酒屋の帆前掛けなどを染めていたんですが、モノがモノだけに、染物を身近なものとして感じていませんでした。でもアルバイトを機に、染物がぐっと身近になったというか。こういう生活に密着した染物をつくりたいなって思うようになりました」

大学卒業後は阿賀野市にUターンし、すぐに実家で染色の修業を始めた野﨑さん。その頃、工場で働いていたのは、60歳を過ぎたベテラン職人3人のみでした。
「いつ引退するかわからないからと、技術を全部教え込もうと最初から100の勢いでこられるので、もう覚えるのに必死で(笑)。大学でも染色の勉強をしましたが、実際に現場に入ると全然違いましたね。使っている染料が違えば、材料、つくり方、時間の置き方、道具、すべて違って」

手ぬぐい存続の危機を乗り越えて
昭和初期から手ぬぐいを製造していた藤岡染工場。でも、当時手がけていたのは、受注した名入れ手ぬぐいのみ。
また、プリントが簡単で、コストの安い名入れタオルが主流になると、名入れ手ぬぐいの受注は激減。15~20年前には、手ぬぐいの製造をやめようという話にもなったのだとか。
けれど、「つくれる会社が少ないいまこそ、手ぬぐいの技術を残していこう」という専務の方針で、手ぬぐいづくりは継続されました。
その後、一般の人にも買ってもらえるような商品をつくろうと、オリジナル手ぬぐいの製造がスタート。野﨑さんも工場に入り、デザインスキルを生かした手ぬぐいや、長岡造形大学との共同制作を企画するなど、藤岡染工場の新時代を築いていくことに。

やがて、世の中の需要は逆転。今日ではタオルよりも手ぬぐいが人気を博すようになり、藤岡染工場のオリジナル手ぬぐいは、そのかわいさ、オリジナリティが話題を呼び、人気商品へと成長していきました。
いまでは工場の責任者を務める野﨑さん。技術を教えてくれた3人の職人は引退し、現在は若い女性を含む6人の職人と一緒に伝統を受け継ぎながら、工場を切り盛りしています。