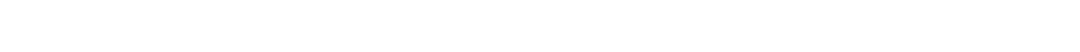コンプレックスだった、高田の「町家」
「マサラ上映」「応援上映」「絶叫上映」といった、ニューウェーブの上映スタイルをとり入れたり、ライブや落語を企画するなど、新しい映画館の在り方を追求する上野さん。ですが前述のとおり、高田にUターンした本当の理由は、まちづくりに興味があったから。

上野さんの実家は高田世界館から徒歩圏内にある「町家」。高田には、奥に長く、間取りや構造もほぼ画一化された、江戸時代から続く町家が並びます。上野さん曰く、この町家こそが彼のコンプレックスだったのだとか。

「町家に対してものすごくネガティブなイメージを持ってたんです。狭いし、暗いし、友だちを呼ぶのも恥ずかしい。かたやテレビで見るふつうの家は広いリビングに光が差し込んでいたりして、そういうのを見ると、さらにひねくれてしまって」
家々が密集し、人との距離が近く、隣家の生活音に常に接するまちの構造と、独特なレイアウトで構成される町家――。これらを真正面から見ることができないまま、大学進学のため故郷を離れて東京や横浜へ。高田とはまるで異なる生活環境で暮らすなかで、地元にいた頃には見えなかったものが目に映ってきたそう。

「高田の町家は、出入り口が向かい合ってるんですね。ゴミを捨てに行くだけでも挨拶を交わしたり、声をかけたり。高田で生きるということは、このまちの構造と同様に、向かい合って生きていくことだと思ったんです。恥ずかしい歴史、恥ずかしい家と自分が思っていたものが、この高田の象徴的なもので、自分も400年前から続く城下町の歴史に連なっているんだ、ということに気づいたというか」

さらに2011年の東日本大震災の際、建築家の山本理顕氏が提案した仮設住宅設計に衝撃を受けたという上野さん。
山本氏のプランでは、被災地住宅の玄関は向かい合わせにし、誰もがいつでも商店を始められるよう出入り口にはスペースを設け、ガラス張りの土間のような場所を玄関先に設けることで、家人の所在や動きが見える設計にするというもの。
「その設計プランをみたとき『ああ、これは高田だ!』って思ったんです。高田の町家の出入り口には“ミセ”と呼ばれる商売スペースがあって、玄関の先には土間があって、家は向かい合っていて。被災地住宅であっても、そこで人の交流が生まれて、商売も生まれれば、そこがひとつの“まち”になるというのを提示してくれたんです。これにはすごく後押しされました」
それ以降、ネガティブに捉えていた故郷への意識が一変。自分たちの住む場所はどうあるべきかを考えたとき、高田というまちや、町家の構造にあらためて興味を持ったと言います。

高田世界館の運営の傍ら、雁木通りの再生保存といった活動にも携わる上野さん。数年前から町家保存を提唱する住民グループもいたようですが、それはほんの一部。ですが、近年になってようやく一般市民も「雁木通りのまち並みを残そう」と声をあげるようになったのだとか。上野さん自身も高田へのU・Iターン者と一緒にDIYで空き家を改修する活動を始めています。
「いま町家というのが高田を表現するひとつの言葉になっています。市の観光のキーワードにも町家が出てき始めました。市民が声をあげてプッシュし続けた結果、市も注目することになったんです。僕はいまでも、町家などに対する引け目みたいなものはなくはないけれど、そういうネガティブなことを、いかにポジティブにしていくかがいまのテーマですね」