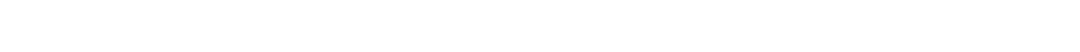Index この記事の目次
- Page 1
- モーニングも楽しめる、コーヒーとサンドイッチの店〈CASUAL DAYS〉
- 高田に現存する最古かつ最大級の町家〈旧今井染物屋〉
- まちの“たて(歴史)”と“よこ(住民)”をつなぐ書店〈たてよこ書店〉
- Page 2
- 少量生産で独創的な酒づくりを目指す酒蔵〈武蔵野酒造〉
- 国産牛のやわらか食感と手づくりの味わい〈ハンバーグ&グリル YUKI MI〉
- 高田城址公園内に佇む端正な数寄屋建築〈小林古径邸〉
- Page 3
- 人気イラストレーター大塚いちおさんが営む〈DIGMOG COFFEE〉
- 市民に愛される日本最古級の映画館〈高田世界館〉
- 読書も「ちょっと一杯」も楽しめる、古本と日本酒の店〈スイミー〉
少量生産で独創的な酒造りを目指す酒蔵
〈武蔵野酒造〉
さて、ここで少し雁木のお話。冬期間でも人々の往来ができるよう、建物の軒下から通行人のために差し出された庇は豪雪地の生活の知恵であり、雁木通りは現代のアーケードの元祖ともいわれています。しかし、アーケードと大きく違うのが、それぞれの雁木やその下の通路は各家の私有地だということ。つまり、個人の土地を歩道として公に提供し、私費を投じて庇をかけているのです。
雁木の下を通ることは、人の家の敷地を通過していることになります。高田の雁木は江戸時代から現在まで続く伝統であり、厳しい冬の暮らしを助け合って生きていこうとする相互扶助の精神のシンボルであるとともに、まちの誇りでもあります。

そんな雁木通りから少し外れ、たてよこ書店から徒歩5分ほどの酒蔵〈武蔵野酒造〉が次の目的地。新潟県には全国一の89の酒蔵がありますが、そのうち上越地方には20蔵があり、そのひとつがこの〈武蔵野酒造〉です。
上越なのに武蔵野? と首を傾げたくなる蔵名は、かつて江戸で蔵人の修業をした創業者が地元の高田に戻る際、江戸の武蔵野周辺の酒屋から酒株(酒造りの営業権)の一部を譲り受けたことに端を発するとか。
代表銘酒は〈スキー正宗〉。高田が「日本スキー発祥の地」であることに由来します。1927年から醸造している銘柄ですが、戦時中は外来語が禁止されたことから、寿亀(すきー)と漢字にして酒造りを続けました。

2020年に大改修を行い、タンクのサイズをかつての15分の1に小型化。少量・受注生産の四季醸造に切り替え、うま酒のある飲み飽きしない酒造りを目指し、同一銘柄でもタンクごとに味わいの違いを感じることのできる小ロットのクラフト酒を提案しています。

珍しいところでは、室町時代に確立された醸造方法で生米を水に浸して乳酸発酵を促す「水酛(みずもと)造り」や、ワイン樽熟成、高温障害耐性米や地元農家が持ち込んだコシヒカリを使った醸造など。こうした独創性溢れる酒は市場にはあまり出回っておらず、蔵でのみ購入できるものも少なくありません。打田さんも手土産や自分用に買いに来ているそうです。
なお、酒蔵見学も3コース用意されていて、新設したこうじ室や仕込み室なども含めて見学できるほか、試飲も可能です。

Information
国産牛のやわらか食感と手づくりの味わい
〈ハンバーグ&グリル YUKI MI〉
まち歩きの空腹を満たしてくれるグルメのお店が揃うのも、高田の魅力。ランチは再び雁木通りに戻り、武蔵野酒造から徒歩12分ほどのところにあるハンバーグやステーキのレストラン〈ハンバーグ&グリル YUKI MI(ゆきみ)〉を目指します。
旧今井染物屋やCASUAL DAYSの南、職人町のなかでも「上職人町」と呼ばれるエリアにあるこの店は、オーナーシェフの新保正行さんの実家だった町家を打田さんがリノベーション。2024年にオープンすると、早々に予約必至の人気店になりました。

店内には12席のテーブル席が設けられ、町家の梁や2階の渡り廊下を生かした吹き抜けの空間が広がります。
新保さんはもともと、妻の三重子さんと東京都世田谷区でレストランを営んでいましたが、70歳を迎え、50年ぶりに地元に戻ることを決意。近隣のCASUAL DAYSのSNSを見たことをきっかけに、10年ほど空き家となっていた実家を改装して店を始めようと思い立ち、連絡を取ったのが打田さんでした。
大きな特徴が、東京の店の設備や厨房機器、什器をそのまま移し、かつての店舗を再現していること。丸ごと活用することで開店資金を抑えることもできたそうです。

提供するメニューも東京時代と同様、国産牛ハンバーグや国産牛ロースステーキ、ビーフシチュー、ハヤシライスなど。良質で無添加の素材と手づくりにこだわり、人気のハンバーグはふわふわとしたやわらかい食感とジューシーさが特徴。160グラム・220グラム・300グラムから選べ、ソースも熟成ガーリックソースや和風ソース、デミグラスソースなど7種類を用意しています。

「夜はお酒も飲めるので、ちょっと贅沢したいときに利用しています」と打田さん。客層は女性が多いそうで、口コミを聞いて遠方から訪れる人も少なくないとか。ちなみに気になる店名は、正行さんの「ゆき」と、三重子さんの「み」を組み合わせたもの。夫婦二人三脚で営む温かい雰囲気も、店の魅力です。
Information
高田城址公園内に佇む端正な数寄屋建築
〈小林古径邸〉
次なる目的地は、駅前から少し離れ、徒歩15分ほどの高田城址公園内にある国登録有形文化財〈小林古径邸〉です。小林古径は上越市出身の近代日本画家の巨匠。明治から昭和期にかけて活躍し、新潟県人で初めて文化勲章を受章しました。その住居だった木造2階建・数寄屋造りの住まいが東京・大田区南馬込から高田城址公園に移築復原され、2001年から一般公開されています。

古径の依頼を受けて設計を担当したのは、同じく文化勲章を受章した建築家・吉田五十八。伝統的な数寄屋建築を基本に、さりげない素材の組み合わせや端正で無駄のない空間構成で、技術と感性を凝縮させました。
「歴史ある建物が地元にあるのは誇らしく、内部に入ると落ち着きます。いまはこのすぐ近くに住んでいるので、桜の時期は花見がてら散歩に訪れています」と話す打田さん。

2020年には小林古径邸に隣接するかたちで〈小林古径記念美術館〉が整備され、清らかで落ち着きのある小林古径の作品を鑑賞することができます。

Information