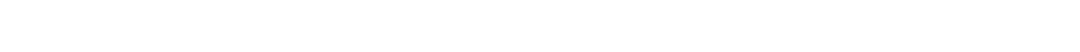世界初の鮭の自然ふ化増殖に成功

青砥武平治は、鮭が生まれた川に帰ってくる習性に着目し、鮭が産卵しやすい環境を整えることを提唱した江戸時代の村上藩士です。
鮭が遡上する三面川に分流をつくり、人工の河川「種川(たねかわ)」とし、世界初の鮭の自然ふ化増殖に成功。村上の鮭文化の礎を築きました。

江戸時代、鮭は村上藩の大切な収入源のひとつでしたが、乱獲のために不漁が続き、藩の財政を圧迫していました。そこで武平治は、鮭をただとるだけでなく、産卵をさせるための「種川」をつくることを藩に進言します。

武平治の考案した「種川」の仕組みとは、三面川の流れを3つの分流にして、ひとつは手を加えず鮭がさらに上流に行けるようにし、ほかふたつには柵を設けて、鮭が産卵しやすいように川底の砂利を整えるというもの。柵の中に留まった鮭が産卵し、ふ化する卵の数を増やすことを狙ったものです。
河川の土木工事は、現代でも大変な労力がかかるものですが、江戸時代に鮭のためにこのような大工事が行われていたとは驚きです。
〈イヨボヤ会館〉の地下フロアを進み、目の前に広がるのは全長50メートルの大観察室。観察窓のガラス越しに見えるのは、なんと三面川の分流(種川)の実際の川底です。ここから種川を遡上する鮭の様子を、自然のままに観察できます。幸運にも、遡上中の鮭とご対面することができました。

村上の鮭料理は「風土」によってつくられる
〈千年鮭 きっかわ〉に戻って、吉川さんに村上の鮭料理についてうかがいます。

「青砥武平治の考案した種川の仕組みによって、三面川にさらにたくさんの鮭が戻ってくるようになりました。これを当時の人たちは天からの恵みだと考えたのでしょうね。『そんな鮭を決して粗末にしてはいけない』『おいしく食べてあげなければ鮭に対して申し訳ない』という感謝の気持ちが、普通なら捨ててしまうような皮、中骨、背腸(せわた)、心臓、胃袋、白子、氷頭、エラまで余すことなく使い切る鮭料理の考案につながったのだと思います」(吉川さん)

「村上では、鮭の内臓を取り出す際に、腹を全部切らずに、腹びれの先で止め、一部を残して胸びれあたりまでを切ります。『藩を救ってくれた鮭を切腹させることは、まかりならん』という鮭を慈しむ気持ちから、今でもお腹の一部を残して切るのです」(吉川さん)
腹を完全に切り開かないこの「止め腹」も、村上独特の塩引き鮭のつくり方です。

鮭への感謝から生まれた数々の鮭料理は、「村上の季節の移ろいとともにある」と吉川さんは続けます。
「毎年12月になると、村上の各家の軒下には塩引き鮭が下げられます。塩引き鮭の材料は、村上の沖合でとれた選りすぐりのオスの鮭と天然の粗塩だけ。ていねいに塩をすりこんだ鮭を、日本海から吹く北西の冷たい風にさらして水分を抜きながら、熟成させます。この村上特有の気候によって鮭自身が持つ酵素が働いて、アミノ酸の旨みへと変わるんですね。
この塩引き鮭をつくる時期は、たとえどんなに寒くても窓は開けっ放し。雪が降っていようが関係ありません。おいしい塩引き鮭をつくるためには、人間のほうが我慢しなければならず、幼い頃から『この家で一番えらいのは鮭で、人間はその次だ』と言われて育ちました」(吉川さん)
「年が明けた正月は、『飯寿司(いずし)』という塩引き鮭を使ったなれずしをいただきます。乳酸発酵が進んだ甘酸っぱい飯寿司は、村上の正月に欠かせない料理です」(吉川さん)

「『鮭の酒びたし』は、塩引き鮭をさらに熟成させてつくったもの。冬の寒さで乾きが進み、春になって熟成が深まり、梅雨の湿気を受けて塩がなれて味がなじみ、秋晴れをもって完熟します。1年を通して完成する鮭の酒びたしには、村上の風土が詰まっていると言えるでしょう」(吉川さん)

お話をうかがってはっきりしたのは、長岡の実家で普段食べていたのは「新巻鮭」で、村上の「塩引き鮭」とはまったく別物だということ。
「新巻鮭」は生鮭の内臓を取り除いて水洗いし、塩漬けにして保存したものですが、「塩引き鮭」は塩を洗い流したあとに、数週間干して熟成させるというのが大きな違い。干すのにどこの土地でもよいというわけでなく、村上特有の気候があってこそ、鮭の熟成が進みます。
鮭は新潟ではとても身近な食材ですが、そのなかでも村上の鮭がなぜ特別な存在なのかがわかった気がしました。