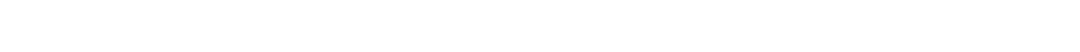Index この記事の目次
おもてなしのまち、摂田屋を巡る
長岡市は南北に流れる日本一の大河・信濃川を中心に山や海など豊かな自然に恵まれ、お米の生産が盛んで、特にお酒の製造が有名です。市内には16の酒蔵元が存在し、その数は県内第1位。
長岡市で日本酒の製造が盛んな理由のひとつに、醸造のまち・摂田屋の存在があります。
かつて江戸幕府の領地として味噌・醤油づくりといった醸造の文化が発達した摂田屋では、今も5軒の蔵元が製造を続けています。腹ごなしを兼ねて、明治・大正期の歴史的な蔵や建物が現役で残る摂田屋のまちを歩きます。

長岡が誇る名建造物
〈旧機那サフラン酒製造本舗〉
〈喜味屋食堂〉から、のんびりまち並みを眺めつつ歩くことおよそ5分。〈旧機那(きゅうきな)サフラン酒製造本舗〉に到着しました。
ここで待ち合わせをしていたのが、〈ミライ発酵本舗株式会社〉取締役統括マネージャーの斎藤篤さんです。〈ミライ発酵本舗株式会社〉は長岡市と摂田屋エリアを愛する人たちが集まったまちづくりの会社。摂田屋のまちを知り尽くした斎藤さんに案内していただきます。

「機那サフラン酒」とは、明治から昭和にかけて「養命酒」と勢力を二分した薬用酒のことです。その「機那サフラン酒」で財を成した長岡の傑物・吉澤仁太郎の屋敷と蔵が〈旧機那サフラン酒製造本舗〉です。
〈旧機那サフラン酒製造本舗〉の敷地はおよそ3000坪。邸宅や米蔵など10棟の建造物、庭園、石垣は醸造のまち摂田屋のシンボルになっており、これらはすべて国登録有形文化財です。特に東洋のフレスコ画とも呼ばれる“鏝(こて)絵”で飾られた蔵には、十二支をはじめとする17種の動物・霊獣・9種の植物が極彩色に描かれています。緻密な細工に、思わず溜息がもれます。



主屋を正面に見て左側には、離れ座敷と庭園が広がります。回遊式の庭園は長野の浅間山から運んだ溶岩でいくつも築山をつくり、佐渡市の赤玉石や糸魚川市の翡翠の原石など、多数の名石のほか、仁太郎自作の石像や石灯籠を配した独創的なつくりになっています。

Information
無農薬・無添加にこだわって作る
〈味噌 星六〉
続いて斎藤さんが案内してくれたのは、〈旧機那サフラン酒製造本舗〉から歩いて1分の〈味噌 星六〉。原料にこだわった古式づくりの味噌は漫画『美味しんぼ』でも紹介されています。

「うちのこだわりは、厳選した国産原料を100%使い、できる限り無農薬栽培の原料でつくっていることです。安心でおいしいものを提供することを大切にしています」(中村さん)

3年もの、と書かれている味噌のパッケージを眺めていたぐっちさんは「大豆から味噌をつくったことがあるんですけど、腐ると思って1年で食べ切ったんです。味噌ってどのくらいもつものなんですか?」と中村さんに質問。
「当社の味噌は呼吸ができる昔ながらの木桶で管理して寝かせているので、何年経ってもおいしく食べていただけます。ただ、小分けしたものをおいしく食べられる目安としては6か月くらいでしょうか。昔ながらの製法でつくると腐りはしないんですが、空気に触れると風味は落ちてきてしまいます。1年以内で食べ切るのがいいと思います」

Information
旧三国街道を散歩しながら
〈越のむらさき〉へ
〈味噌 星六〉を出ると、今度は旧三国街道へ。蔵元の建物の間を通るこの街道を歩くと、ふと醤油や麹の香りが風に乗って運ばれてきます。

香りの正体は、旧三国街道を抜けた先にある〈越のむらさき〉。江戸時代から醤油をつくり続ける老舗です。明治10年(1877年)に竣工した社屋は登録有形文化財に登録されました。

さらに歴史が深いのが、越のむらさき入口にある「道しるべ地蔵」です。
「200年以上前につくられたお地蔵様で、ここは三国街道の分岐点でした。台座には『右ハ江戸左ハ山路』と彫られています。江戸時代に江戸へ旅する人が道中の無事を祈ったと言われています」(斎藤さん)

Information
雁木スペースでいただく
焼きたての〈江口だんご〉
〈越のむらさき〉から〈江口だんご 摂田屋店〉は徒歩2分。〈越のむらさき〉創業家の旧邸宅を改築して、2022年7月にオープンしました。実はぐっちさん、江口だんごを食べたことがないそうです。「めちゃくちゃおいしいよ」とチカポンさんもおすすめします。

緋毛氈(ひもうせん)が敷かれたベンチに座り、お団子の焼き上がりを待っている間、「実は、今日少し待ち合わせ時間より早く着いて、暇だったからコンビニで肉まん食べたんだよね」とチカポンさん。「普通、時間あるからって肉まんを食べよう、とはならないよね」とふたりの食べっぷりの良さがわかるエピソードが飛び出します。



〈江口だんご〉は明治35年(1902年)創業。初代の江口駒吉が信濃川の中州で行き交う人々にだんごや煮しめなどを賄う茶屋を出したのがはじまりです。摂田屋店では、焼きたての串だんごのほか、笹だんごやどら焼き、お饅頭など摂田屋の発酵食品を使った限定の〈蔵元菓子〉も購入できます。
Information

〈江口だんご〉を出て、〈旧機那サフラン酒製造本舗〉の〈発酵ミュージアム・米蔵〉へ戻ってきたふたり。セレクトショップ内では摂田屋エリアの発酵食品や人気作家が手がけたハンドメイド作品などが並んでいます。

「明日、東京の友人と会うんです」と話すチカポンさん。ぐっちさんと一緒に、友人が喜んでくれそうなお土産探しに夢中になっていると、どこからともなく美しい旋律が……。


もともと20年くらい放置されていたピアノですが、〈米蔵〉に寄贈されてからは訪れたお客さんたちが弾いてくれたことで、だんだんと音が柔らかくなっていきました。斎藤さんも積極的に触るようにしているそうです。
古い建物を壊して新しく建て替えるのではなく、古いものを磨いて再生していく。人の手が加わることで古くなったものも熟成されていくといいます。
摂田屋を知り尽くした斎藤さんに新潟のコメジルシを聞いてみると、「摂田屋エリアですね。発酵・醸造の文化が根づいている、唯一無二の地域であるこの摂田屋エリアが新潟のコメジルシです」と答えてくれました。