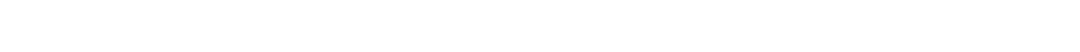新潟は“地元でひとり占めしたいごちそう”の宝庫
新潟の食は「お米と日本酒」だけではありません。実は、地元の人にとっては日常の食事でも、県外にはあまり出回らないごちそうが数多くあります。
象徴的なのが枝豆。新潟県は枝豆の作付面積で全国1位ですが、出荷量は全国8位にとどまります。(出典:令和5年度 農林水産省「野菜生産出荷統計」)つまり、生産量は多いのに多くは県外に出ず、地元で消費されているのです。“新潟えだまめ盛”と命名されたザルいっぱいの枝豆とビールが食卓に並ぶのは、新潟ならではの風景。

豊かな自然と暮らしが育んだ食文化があるからこそ、「本当は教えたくなかった!」と地元の方も思うごちそうがあるのです。そんな新潟の7つのグルメを、新潟県民が魅力を発信している「コメジルシプロジェクト」からピックアップしてご紹介します。
地元だからこそ知っている新潟グルメ7選
寺泊のズワイガニと地酒の贅沢マリアージュ

冬に解禁される越後本ズワイや紅ズワイ。長岡市の寺泊・魚の市場通りでは、塩加減よく茹でられたカニがずらり。ここで購入して“自宅で豪快に食べる”のが、地元情報誌『〈新潟Komachi』佐藤亜弥子編集長の楽しみ方。合わせるのは、同じ長岡の朝日酒造(〈久保田〉〈朝日山〉)。

「最後の晩餐は迷わずカニ」と語る佐藤さんいわく、冷酒や熱燗、甲羅酒まで含めて至福の一席になるのだとか。新潟の家庭にとっては毎冬のお楽しみ。だからこそ、県外の人にとっては“とんでもなく贅沢な体験”と思えるごちそうです。
(佐藤亜弥子さん/新潟市)
津南町の「採れたてをかじる」高原野菜

豪雪地・津南町は、「農を以て立町の基と為す」と町是として掲げるほど、農業を基幹産業にして成長してきた地域。雪解け水に富み、寒暖差のある土地が日常のごちそうを生んでいます。
そんな津南町で露地野菜を育てる飯吉友恵さんは、「自分たちの畑で生のままかじれる野菜をつくること」を掲げ、雪下にんじんやアスパラ、長ねぎを栽培。通常、収穫から店頭で手にするまで短くても3~4日はかかるのに対し、採ってすぐ食べる圧倒的なみずみずしさは現地ならではと、飯吉さんは語ります。

おすすめは、〈雪下にんじん〉を生で味わうこと。見ているだけで甘さが伝わってきます。素材がよくて新鮮だとシンプルにいただくのが一番ですね。
(飯吉友恵さん/津南町)
サザエが100円均一!? 佐渡の海鮮日常価格

佐渡に移住したイシハラマサミさんが驚いたのは、サザエが1個100円前後で店頭に並ぶこと。メバル、真鯛、ブリなども手に入りやすく、スーパーの魚が基本“刺身でいける鮮度”というのも島ならではと語ります。佐渡はマグロもとれるので、回転寿司のマグロも最高においしいのだそう。

近所から新鮮な魚をもらうこともある暮らしは、海の恵みと人の距離が近い証拠です。都会では高級な海産物も、ここでは当たり前。日々の食卓に根づいていることが、佐渡の海の“豊かさの本質”と言えるでしょう。住んでみてより実感できるグルメですね。
(イシハラマサミさん/佐渡市)
阿賀町で「馬レバ刺し」と地酒を

福島県に隣接する阿賀町は、かつて会津藩だったことから、会津の馬食文化が今でも残っているそうです。阿賀町で生まれ育った高橋眞也さんは、子どもの頃から馬刺しが身近だったと語ります。高橋さんが大人になって知ったのが、地元の精肉店〈あおやぎ肉店〉で手に入る馬レバ刺し。鮮度が要のため、地元だから出合える味です。

馬レバ刺しに合わせたいのは地元の日本酒〈麒麟山〉。これぞ、教えたくないけど自慢したい地元の味。土地に残る食文化と小さな流通圏が、そのおいしさを守っているのでしょう。
(高橋眞也さん/阿賀町)
雪室熟成で旨み凝縮〈越後川口の生ハム〉

長岡市川口地域には、季節の温度変化と雪室の環境を生かした〈越後川口生ハム塾〉があります。監修は東京で熟成肉やジビエのレストランを経営する神谷英生シェフ。県産ブランド豚のモモ肉+塩のみで仕込み、雪室で約1年半熟成。薄く切っても肉の旨みが濃く、この地ならではのおいしさを実感できます。

神谷シェフ曰く、川口地域は生ハムづくりにぴったりの地域なのだとか。雪深い地域と、温度・湿度が安定する雪室という生活の知恵が背景にあるから。味わうまでに少々時間がかかりますが、時とともに熟成されたおいしさを実感できる新潟グルメです。
(mkさん/見附市出身)
幻の甘さ、刈羽村の〈砂丘桃〉

刈羽村で昔から栽培されてきた〈砂丘桃〉は、市場にほぼ出回らず、直売所や農家の前で出合える“幻の桃”。糖度18〜20度に達することもある濃い甘さは、水はけのよい砂丘土壌と昼夜の寒暖差という条件が生むもの。

砂丘桃を教えてくれた布施弘樹さんは、初めて食べたときの程よい食感としっかりとした甘さの虜になり、自分の会社でも栽培するまでに。近年では、農家の高齢化や跡継ぎ問題も課題となっていますが、「砂丘桃が刈羽村の特産品として10年後、100年後まで続いてほしい」と、活動されています。
(布施弘樹さん/柏崎市)
人気料理家の大好物! ナスの三五八漬け

新潟県見附市出身の料理家・坂田阿希子さんが新潟の魅力に挙げたのは、ずばり、野菜。特にナス。子どもの頃から夏のナス漬けが大好物で、上京後も新潟のナスを三五八(さごはち)漬けにして味わってきたといいます。

新潟県は古くからナスの産地であり、各地域で異なる品種を育てていて、11種類が〈にいがたの伝統野菜〉に指定されているほど。見た目にも楽しいバラエティに富んだナスが楽しめます。
“おいしい野菜が日常にあることの贅沢”という坂田さんの実感は、一度地元を離れたからこその視点。食卓に根づいた食に新潟の良さが宿ります。もしかしたら料理家の原点がここにあるのかもしれません。
(坂田阿希子さん/見附市出身)
大地と雪の恵みを、暮らしの距離で味わう
ここで紹介した7つのグルメは、「名物料理」や「B級グルメ」ではありません。そこに暮らす人たちが日常の暮らしで食べ、語ってきた“生活に根づいた味”です。
新潟という土地ならではの食材と食文化。旅の途中でこれらに出合ったら、料理そのものだけでなく、それを語る人や土地の背景にも目を向けてみてください。きっと、ひと皿の味わいがより深く感じられるはずです。
credit credit text:新潟のつかいかた編集部